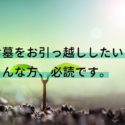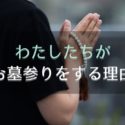【必要な情報を全展開】墓じまいの流れと費用|墓石解体・撤去で失敗しないためのガイド
少子高齢化やライフスタイルの変化に伴い、「墓じまい」を選ぶ方が増えています。
しかし、墓じまいには多くの手続きや費用が発生し、準備不足で後悔してしまうケースも少なくありません。
本記事では、墓じまいの流れ・種類・費用について、必要な情報を分かりやすく解説します。
墓石解体や撤去で失敗しないためにも、ぜひご参考ください。

| 目次 |
| 1. 墓じまいとは? |
| 2. 墓じまいの種類と選び方 |
| 3. 墓じまいの流れ|手続きと依頼先 |
| 4. 墓じまいにかかる費用 |
| 5. お墓参り代行について |
| 6. 墓じまいで失敗しないためのポイント |
1. 墓じまいとは?
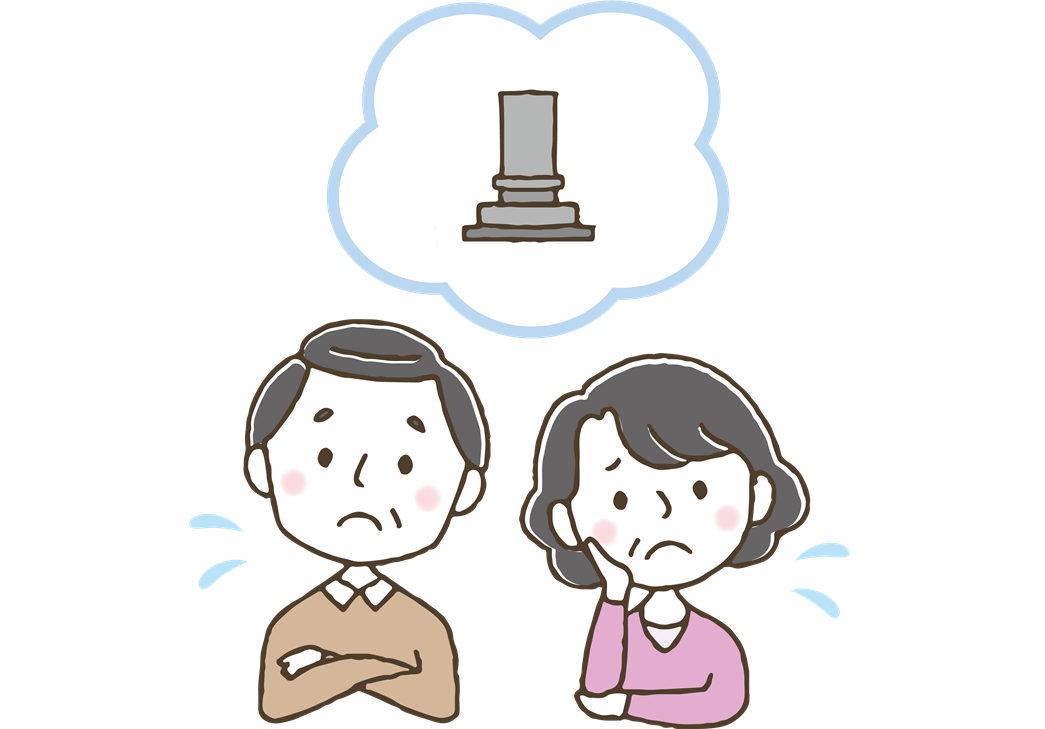
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、ご遺骨を新たな場所に移動する手続きのことです。
墓じまいを考える主な理由
- ・お墓の管理が困難:遠方に住んでいるためお墓参りが難しい
- ・後継者がいない:お墓を守る人がいない
- ・経済的な負担:維持管理費が重い
放置されたお墓は「無縁墓」として整理される可能性もあるため、事前の計画が重要です。
2. 墓じまいの種類と選び方
墓じまいの際、ご遺骨をどう供養するかを決める必要があります。主な選択肢は以下の通りです。
- ・納骨堂:一定期間安置し、その後合祀される場合もある
- ・合祀墓(永代供養墓):他の遺骨と一緒に供養され、管理の負担がない
- ・樹木葬:樹木を墓標とする自然葬
- ・散骨:ご遺骨を海や山に撒く方法
注意:散骨は元に戻せないため、家族や親族と十分に話し合いましょう。
お墓自体を完全に整理して墓じまいを行うにあたり、お墓に安置してあるご遺骨をどうするかが重要です。
上記のとおりご遺骨の引っ越し先の選択肢としては納骨堂、合祀墓、樹木葬、散骨などが挙げられます。
納骨堂の場合は決まった期間ご遺骨を安置し、その後は合祀供養される場合など場所によって様々です。
永代供養の合祀墓・樹木葬等であれば将来にわたって管理や供養をしてもらえるため、遺された家族への負担を考えて選択する方もいるでしょう。
次に散骨ですが、散骨の場合はご遺骨が手元に残らず、手を合わせる場所もなくなってしまうことからよく考えて選択する必要があります。
実際にトラブルになった事例もあり、一度散骨してしまえば後悔しても状態を元に戻すことは不可能です。
ご家族など、関係者の方とよく話し合って選ぶようにしましょう。
ご自身やご家族にとってこれからどのような供養のかたちが適しているのかをじっくり話し合い、それに見合った墓じまいを検討することが大切です。
3. 墓じまいの流れ|手続きと依頼先
墓じまいの手続きには以下のステップが必要です。
墓じまいの流れ
- 1. 家族・親族の同意を得る
- 2. ご遺骨の移転先を決める
- 3. 墓地管理者に相談し、改葬許可申請を行う
- 4. 閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出す
- 5. 石材店に墓石の解体・撤去を依頼する
- 6. 土地を管理者に返還し、ご遺骨を移転先で供養する
依頼先の選び方
墓じまいは石材店に依頼するのが一般的です。
- ・見積もりを事前に取る
- ・現場確認で追加料金の有無を確認する
石材店へ依頼する前に、親戚一同ときちんと話し合っておくことも重要です。
後のトラブルを防ぐためにも必ず同意を得たうえで墓じまいをすることをおすすめします。
順序としては、まず親戚一同の同意を得てご遺骨の行き先を決定します。
その後、現在お墓のある霊園や墓地の管理者に墓じまいをしたい意向を伝え、改葬許可の手続きを行うために各種書類を準備するという流れです。
墓じまいするためには必ず改葬許可書を取得する必要があります。
手続きが済んだら、あらかじめ頼んでおいた石材店にご遺骨を取り出してもらうことになります。
その際、宗派によっては閉眼供養を行います。
ここまで済ませたのち、石材店がお墓の解体に入ります。
墓じまいが完了するとお墓があった場所は更地に戻ることになるため土地を管理者に返還し、残ったご遺骨をあらかじめ決めておいた方法で供養することになります。
注意:
まれなケースではあるものの土葬により火葬できていないご遺骨が見つかることがあります。
その際は再火葬が必要となりますので、戦中から戦後の混乱期のご遺骨が眠っている可能性が考えられるのであれば、再火葬における追加費用というのも頭に入れておかなくてはなりません。
4. 墓じまいにかかる費用
墓じまいをする際、具体的にどのような費用が掛かるのでしょうか。
墓じまいに掛かる主な費用をまとめました。
必要書類の交付手数料
墓じまいをするためには、改葬許可証や受入証明書、埋葬証明書などの書類が必要です。
それぞれ、自治体や霊園・寺院から発行してもらう必要があります。
基本的には無料で発行してもらえますが、中には手数料が掛かる場合もあるため、気になる方は確認が必要です。
また、有効期限が定められていることが多いので、手続きは早めに行いましょう。
閉眼供養
閉眼供養ともに、僧侶に読経してもらうことになるため、お布施が必要になります。
お布施の相場はあってないようなものですが、概ね3~5万円程度が多いのではないでしょうか。
また、閉眼供養の法要後には会食の席を設けるのが基本ですが、僧侶が会食を辞退されることもあり、その場合は御膳料として1万円程度を別にお包みするのが一般的です。
離檀料
菩提寺にあるお墓を墓じまいする場合は、檀家をやめるケースも考えられます。
その際、お世話になった感謝の気持ちで離檀料をお布施として渡します。
中には受け取らないお寺もありますが、渡す際の相場は今までのお布施の3回分、約10~15万円程度でしょう。
離檀料のお布施と法要の際のお布施とは別なので注意が必要です。
解体費用
墓じまいをするため、お墓の解体を石材店などに依頼することになります。
解体費用はお墓がある現場状況や、お墓のボリューム、作りなどの条件次第で様々です。
九州の中でも特に長崎県では、勾配のきつい場所に大きなお墓が建っている場合も多く、費用がかさむ傾向にあります。
先に現場を確認してもらうことで、後から追加料金を請求されるというトラブルを防ぐことができるでしょう。
ただし、お墓次第では解体してみないとわからないケースもあるため、そのような場合には事前に伝えてもらえる石材店だと安心です。
納骨費用
墓じまいを行うには、新たな納骨先を準備していなくてはいけません。
納骨堂に移す場合はもちろん、合祀墓や納骨せずに散骨する場合にも費用は発生します。
供養形態や料金はさまざまですので、家族や親族ともしっかり話し合い決定しましょう。
お墓参り代行について
お墓参り代行をご存知でしょうか?
墓じまいを考える理由のひとつに、お墓参りに行きたくても行けないということが挙げられます。
そのような方たちに、是非検討していただきたいのがお墓参り代行です。
現代の日本人のニーズにあわせて登場したサービスで、お墓が遠方にある方や多忙で時間がない方たちの代わりにお墓の掃除やお参りなどを行ってもらえます。
お墓参り代行については下記に詳しく記載しております。
6. 墓じまいで失敗しないためのポイント
墓じまいは後悔しない計画性が重要です。
ポイント1:家族や親族との話し合い
トラブル防止のため、必ず同意を得ることが大切です。
ポイント2:信頼できる石材店を選ぶ
口コミや実績を確認し、信頼できる業者に依頼しましょう。
ポイント3:改葬手続きの準備
改葬許可証の申請には書類が必要です。事前に確認しておきましょう。
墓じまいを行うには多くの手続きを必要とし、確認点も多く、労力や金銭的な負担が大きいのが現状です。
しかし、後継者が存在しない無縁墓は一定期間が過ぎると管理者によって整理されてしまうこともあるため、できれば避けたいものです。
そうなってしまう前に親族ときちんと話し合い、どのタイプの墓じまいが合っているのかを考えることは必要なことといえるでしょう。
また、墓じまいの理由によってはお墓参り代行などのサービスを利用することで墓じまいを避けることもできます。お墓がなくなってしまうことで心の拠りどころがなくなってしまう場合もあるため、後悔しないよう慎重に選択しましょう。
くようのコトナラでは、墓じまいに関するご相談を随時受け付けております。